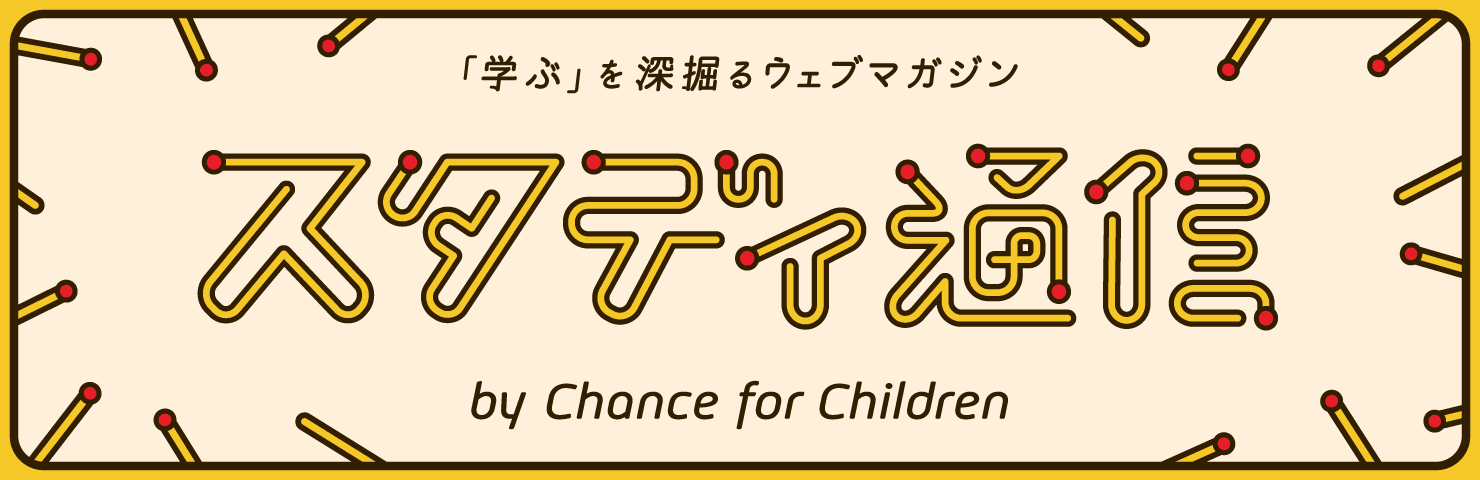「壊れかけの家族」から逃げられる場所。少年時代をギリギリ生き抜いた彼が小さな塾を作って気づいたこと(「渡塾」渡剛)
大阪府箕面市。緑に囲まれた閑静な住宅街の一角に小さな塾がある。

多くの人がイメージする「進学塾」とは少し異なる。ここは、ひとり親家庭の子どもたちを支えるために設立された塾だ。塾の名前は「渡塾(わたりじゅく)」。今年で10年目を迎えた。
塾長の渡剛(わたり つよし)さん(29)は、自身が未婚のシングルマザーの家庭で三人兄弟の末っ子として育った。母は保険会社の外交員として働き、一人で育ててくれた。父はどんな人なのかも知らず、一度も会うことがないまま渡さんが18歳のころに他界したと聞いた。
小学生のころは大きな困り事なく過ごしたが、中学生になると家庭の状況が一変。兄が抱えた借金、祖母の介護によって、母一人で支えていた家庭が大きく揺らいだ。
毎晩のように母と兄の怒鳴り声が聞こえ、借金の取り立て電話が鳴り止まない日々——。家が安心していられる場所ではなくなった。母に「死にたい」と手紙を書いたこともあった。

その後、渡さんは様々な苦難を乗り越え、経済的な事情で一時は諦めた大学に進学。在学中、自分と同じような境遇にあるひとり親家庭の子どもたちを支えようと、「渡塾」という小さな塾を立ち上げた。
現在は、7名の職員、約80名の大学生らとともに塾を運営している。塾にはフリースペースで過ごす子もいれば、大学生とおしゃべりをしにくる子もいる。食事ができるスペースもある。
近年は、ひとり親家庭の子だけでなく、勉強嫌いな子、不登校の子、家庭に困りごとを抱えている子など、様々な背景を抱える地域の子どもたちが渡塾にやって来るようになった。そして、渡さんはあることに気づいたという――。
今回は、渡塾にお邪魔させてもらい、渡さんから、ひとり親家庭で育った自身の生い立ち、塾を立ち上げた経緯、子どもたちと関わる中で学んだことについて、話を聞かせてもらった。

兄の借金、祖母の介護を契機に家庭が一変
――渡さんは、どんな子ども時代を過ごしましたか?
僕は熊本で生まれ、未婚のシングルマザーである母に育てられました。母と僕、10歳以上年齢の離れた2人の兄、祖母の5人家族でした。母は保険会社の外交員で営業成績もすごく良くて、会社から表彰されたりもしていたようでした。稼ぎもちゃんとあって。
幼稚園のころから体操教室、そろばん、書道教室など、複数の習い事をさせてもらっていました。小学生のころは夏に毎年キャンプにも参加していました。誕生日には、友達を家に招待して誕生日パーティーを開いたり。クリスマスにはちゃんとサンタクロースからのプレゼントも届きました。本当に「普通」の生活を送ることができていたと思います。

母は仕事で帰りが遅い日が多かったので、幼稚園のクラスの中で、僕だけ送り迎えは祖母にしてもらっていたというのはありましたが、特にそれで嫌だと思ったこともなかったですね。でも、そんな生活が中学生のころに一変したんです。
――中学生の時に何があったんですか?
家庭で二つの事件がほぼ同時に起きました。一つは、実家を離れて一人暮らしをしていた兄が借金を作ってしまったこと。もう一つは、祖母が骨折して介護が必要な身体になってしまったため、母が働く時間を減らさざるを得なくなってしまい収入が減ってしまったことです。

――それは大変でしたね…。お兄さんの借金の話は、お母さんから事情を聴いたんですか?
いえ、中学2年の夏休みに、家でゲームをしてたら、知らない男の人から電話がかかってきて、「○○(兄の名前)いますか?」って言われたんです。
兄はその時、家にいなかったので、「いません」って答えたら、「いませんじゃなくて、出さんか!おらあ!」ってすごい剣幕で怒鳴られて。「え…」みたいな感じになって。びっくりしました。
その男の人から、「自分、誰なん?」って言われたので、「弟です」と答えたら、「夏休みにのんきに遊んでる場合じゃないんや!」ってまた怒鳴られて。「金を借りて逃げてんだよ、お前の兄貴は。電話に出せ!」って言われました。
「本当にいないんです」と言うと電話は切れました。この電話で、「これは何かとんでもないことが起きているぞ」と察しました。
母が家に帰ってきて、電話のことを話したら、兄が借金をしてしまったという事情を知らされました。それ以来、知らない電話番号からの電話をとるのが怖いというか、今でもトラウマになっています。

家に「安心できる場所」がなかった
――事件後、生活はどのように変わりましたか?
借金のことがあって、兄が実家に戻って来ました。それから家では、母と兄が毎日、借金のことでけんかをしていて、怒鳴り合っていました。明らかに、母が精神的にしんどそうになっていました。
母の帰りが遅くて、ご飯も「勝手に食べておいて」っていう日も増えましたし、お酒を飲んで酔っ払って帰って来ることもありました。ある日の夜、兄と母が口論をしていて、「剛と一緒に死んでやる」と母が泣き叫ぶ声が聞こえてきたこともありました。
それから、借金の取り立ての電話がしょっちゅう鳴るようになりました。とにかく電話がかかってくるのが怖くて…。留守番電話に過激なメッセージが残されていることもありました。あの時期は、家にいても落ち着くことが全然できなくて。

――大変な生活でしたね。家の外ではどのように過ごしていたんですか?
当時は、とにかく家の中にいたくありませんでした。一人でいるときに電話がかかってくるんじゃないかっていうのも怖かったですし。なので、僕は中学校では生徒会もやっていたんですが、中学校の門が閉まるギリギリまで学校にいるようにしていました。家に帰りたくなかったので。
――学校が終わった後は家に?
いえ、塾にいました。中学1年生のころから塾に通ってたんです。ひとり親家庭は授業料を割引してくれる塾なんですけど。
でも、あの事件以降、最初のころは塾も休みがちになってしまって、成績が一気に下がってしまったことがあって。それで、家にいなくてもいいし、学校が終わった後は塾に行こうと。
学校が終わって、夕方5時から夜10時くらいまでは塾にいたと思います。授業がない日も、自習してたり、夜ご飯も買って塾で食べたり。

塾にいるときは、家のことを考えなくてもいいし、放課後唯一心が落ち着く場所でした。別に誰かが話を聞いてくれるわけではないけど。単に家にいなくていいだけで気持ちが楽でしたね。
中学生の僕にとって、塾は勉強さえしていれば、いくらでもいていい場所というか。合法的に家にいなくても済む場所って感じです。「塾に行ってくる」と言えば、親ももちろん納得してくれるので。だから受験生のときなんかは、土日もずっと塾にいましたね。
――勉強は好きだったんですか?
勉強することが習慣みたいになっていたので、楽しいとか嫌いとかもなく、単純にテストで点数が上がったら嬉しいという感じでやっていました。
それよりも塾にいると、家庭のことを忘れることができて、家にいなくていいというのが一番大きかったと思います。プロの先生が勉強を教えてくれて、友達もいる。そういう環境が、自分にとってはよかったんだと思います。

あと、僕が勉強を頑張ることで、母には安心してもらいたいという気持ちもありました。
母は、僕が小さいころから「剛が頑張ることが私の生きがいだ」と言っていました。その期待に応えようと思って、生徒会に入ったり、勉強も頑張ったりしてきました。なので、「僕がここで頑張るのを辞めてしまったら、お母さん死んじゃうんじゃないか」とか、そういう思いもありました。
――当時は、お母さんとはどんな関わりをしていたんですか?
僕から母に話しかけることは、ほぼなくなりました。明らかに母の余裕がなくなっていくのがわかったので、余計なことを考えさせたくないというか。とにかく、親にこれ以上負担をかけないようにしようと。
だから、何かあってもなかなか母に相談することができなかったです。特に、お小遣いをもらうのは気が引けました。受験生の時に、1,000円の参考書を買ってもらうのにもすごい勇気が必要で。母には、意を決して「参考書を買ってもらえないか」と言ったのを覚えています。

立ちはだかる大学進学の壁
――そんな中で高校受験を迎えたんですか?
塾で勉強していたおかげもあって無事に志望していた公立の高校に合格することができました。行きたかった高校は、母の母校でもありました。
高校に進学してからは、とりあえず兄の借金の問題は、弁護士さんに相談して落ち着きました。詳細はわからないのですが、家に電話が来ることもなくなりました。
ただ、祖母の介護はその後もずっと必要だったので、母が仕事をフルでできない状況は続き、経済的な部分は高校に入った後も悪いままでした。相変わらず、「低空飛行」な感じですね。それ以上悪くなることもないというか。

――高校卒業後のことはどう考えていたんですか?
当時、教師になりたくて、大学進学を目指していました。小学5年か6年生の時の担任の先生が23歳の新任で、その先生の家に休みの日に遊びに行ったりもして、「先生のようになりたい」と憧れたのがきっかけです。日常的に接する大人の男性が初めてだったというのもあったと思います。それが、たまたま学校の先生でした。
ただ、国公立大学でも、初年度の入学金や授業料だけで100万円は必要だと聞いて、「100万円なんてお金、うちにはないぞ」と。当時は、周りの友人の影響もあって、熊本を出て関西か東京の大学に行きたいと思っていたので、それだともっとお金がかかる。
それでも、母は「お金のことはなんとかするから、あなたは心配しなくていい」って言ってくれました。その言葉を信じて、大学受験に励んでいました。でも、そんな時にまた事件が起こりました。

――何があったんですか?
高校3年の秋、受験の直前でしたが、一人暮らしをしていた兄が、また借金をしてしまったんです。それで、「いよいよ、これは無理だ」と。大学進学は諦めなくてはいけないと思いました。
僕、必死に受験勉強頑張ったのに、もう、どうにもできないんだと。教師になるの、小学生からずっと夢だったのに、諦めなくてはいけないんだと。
自分の部屋で勉強していたときに、「勉強したって意味ないじゃん」「どうせ無理なんでしょ」ってなって。それで「死にたい」って手紙に書いて、リビングにいた母に渡しました。
それを読んだ母に泣きながら謝られて…。とりあえず、落ち着いて勉強ができるよう、母から兄に、僕の受験が終わるまで、家に戻って来ないように言ってくれました。でも、お金の問題は残りました。

――大学進学はどうすることになったんですか?
大学進学を諦めかけていた時、突然、父が亡くなったという知らせが入ってきたんです。それで父の遺産が相続されることになって、大学進学の費用を工面できることになりました。
当時は、非嫡出子(法律上の婚姻関係がない男女の間に生まれた子ども)には、嫡出子の相続分の2分の1が贈与されるということで(※2013年に民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の相続分は同等になりました)、奇跡的に志望していた国立大学にも合格でき、大学に入学することになりました。
でも、実際はそれよりも父が亡くなった時のショックの方が大きくて。僕は父のことは写真で見たことがあるだけで、一度も会ったことがなかったんですけど、20歳になったら、一度父に会ってみたいと思っていたので。亡くなったと聞いて、頭の中が真っ白になりました。涙が出てきて。「父にもう会えないんだ」ってなって。
今の塾を立ち上げて、本当にうまくいかなかったときも、父はどんな声をかけてくれるんだろうって思ったりとかもしました。今は、父がいなかったら大学進学できなかったので感謝しています。

「あなたのような人を待っていたの」。シングルマザーの声を聞き、塾を設立
――大学に入ってからはどんな生活でしたか?
大阪に下宿しました。学費は授業料減免を受けて、生活費は日本学生支援機構の貸与型奨学金を月10万円ほど借りて、生活していました。奨学金は、今も返し続けています。それと、家庭教師のアルバイトをしたり、当時800円くらいの時給の弁当屋でアルバイトをしていました。サークルは、大学の学園祭の実行委員に入って活動していましたね。
――大学ではどんな勉強を?
外国語学部に入学しましたが、1年生のころは一般教養として、学部関係なくいろいろな授業を受けていました。
その中で、「子どもの貧困と教育格差」についての授業がありました。教師になりたかったということもあり、教育格差に少し関心があって授業を取りました。

『子どもの貧困』(阿部彩著、岩波新書)という本が授業の課題図書だったのですが、その本の中に母子家庭のエピソードが載っていました。朝から晩まで働いていて、身体が動かない、でも、仕事を休んだら生活していけない。もう体も動かないし、死ぬしかない、といったお母さんの声が紹介されていたんです。
「なんでここまで追い込まれてるのに、誰も助けてくれないんだろう」、「なんで親が1人ってだけで、こんなにしんどい思いをしないといけないんだろう」って感じて。自分の家庭と重なる部分があって、家で本を読みながら泣いたのを覚えています。

――それで今の塾をはじめたんですか?
当時は、いつか何か力になりたいなと漠然と思っていて、まだ自分で何か始めるという発想には至っていませんでした。でも、ちょうどそのときに、大学の友人がビジネスプランコンテストを主催する団体でインターンをしていて、その友人に頼まれて、たまたまそのコンテストに出場することになりました。
無料で通える学校を作るっていうプランで、今考えるとビジネスプランでも何でもないんですけど…。高校時代の友人にも手伝ってもらいながら、ファイナリストまで選んでもらって。 そのプランをブラッシュアップする合宿に参加して、色んな大人の人たちから意見を言われたんです。
「無料で通える学校を作りたいなら、文科省に入れ」って。「そもそも、ひとり親家庭の子どもの困りごとって何なの?あなた当事者なんでしょ」と。「僕が一番困ったのは大学入学の時のお金でした」って答えました。じゃあ、そのための、奨学金制度をつくろうってことになりました。
そこで、実際にひとり親家庭の当事者の声を聞きに行きなさいって言われたんです。当事者か、当事者のことをよく知ってる人に話を聞きに行きなさいと。当事者の知り合いがいないなら、親の会を探して、自分で会いに行きなさい、と。

――それで、実際に会いに行くことに?
はい。大阪でシングルマザーの「おしゃべり会」が開催されるということを知って、連絡先もわからなかったので、アポなしで、会場の前で待っていたんです。部屋の方に歩いてくる女性の方がいて、「すみません。僕、大学2回生で、ひとり親家庭の子どものための奨学金制度を作ろうって考えているのですが、お話を聞かせてもらえませんか」と話しかけました。
すると、ぱっと両手で僕の手を握って、「あなたのような人を待っていたの」と言われたんです。アポなしで行ったので、怒られるかなとか、追い返されるかなとか思っていたんですが、そう言ってもらえてびっくりしました。
この体験が自分の気持ちの転換点だったというか。初めて人から必要としてもらえた瞬間だったんです。実際に当事者のお母さんと接することで、自分の心に火が付き始めているのを実感したみたいな感じで。
帰りに原付に乗りながら、こういうことを本気でやっていくのも、悪くないのかもと、ぼやーっと考えていました。プランの中に塾の設立というのもあって、最終的にはその事業をやってみようということになりました。

「渡塾」の立ち上げ
――そんなきっかけで、塾を立ち上げることに?
そうですね。たまたま、そのとき立ち上げ資金200万の支援を受けられる内閣府の事業があったので、それで立ち上げ資金を得て、大学時代の友人に手伝ってもらいながら、塾を立ち上げました。
――最初はどんなことで苦労しましたか?
最初は、物件を借りるのに苦労しましたね。まだ学生だし、ひとり親家庭の子どもを支えたいとか言っていて、こいつ家賃払えないだろって思われて、なかなか借りられなかったです。でも、たまたま出会った不動産会社の人で、ご自身がシングルマザーの方がいて、そういうことであれば、力になりたいと言ってくれました。
仲が良いオーナーさんがいるからその人に交渉してみると言ってくださって、もしその人が良いって言ってくれたら、その物件でいいですか?と聞かれて。テナントとして使ってもいい、1LDKで家賃7万8千円の住居用の一室でした。

ここで全然大丈夫ですということで交渉していただいた結果、保証人を2人立ててくれたらいいよということになりました。それで、母と、母の知り合いの方に保証人になってもらって、無事物件を借りることができたんです。
――すごい偶然の出会いですね。そこから生徒を集めていったのですか。
そうですね。ポスティングでチラシを配って回りました。チラシには「ひとり親家庭の子どもを支えるための塾」っていうコンセプトをうたいました。一つは料金的に安いということ、もう一つはひとり親家庭で育った当事者の僕がやっているというところを打ち出して。

最初は、大阪の「おしゃべり会」で出会ったひとり親家庭の子ども、大学の友人の知り合いのひとり親家庭の子ども、塾の看板を見て飛び込んできてくれた子どもの3人の生徒が入塾してくれて、塾が始まりました。講師は大学の友人とか後輩とかに手伝ってもらいながら、という感じです。
そこから、だんだん生徒の口コミとか、生徒が友達を連れて来てくれたりとかしながら、生徒が徐々に増えていきました。今は、箕面市だけでなく、高槻市などでも塾を開いたり、行政からの委託を受けて家庭に大学生講師を派遣する活動へと広がっていっています。

日常の「安心」がない子どもたち
――塾を始めてから10年で何か変化はありますか?
最初はお金がなくて普通の塾に通えない子に、勉強だけを教えていればいいと思っていました。でも、最初、子どもが全く宿題をしてこなくて。「小テストをやるから、ここを覚えてきてね」と言っても、全く覚えてこない。
「どうせ、勉強しても点数とれへんから、別のことやっててもいいですか」と言ってきた子がいて、「やる気がないなら塾を辞めていい」と言ってしまったこともありました。
最初は「なんで勉強しないの?」って思ってたんですよ。「ここ塾だよ」って。自分は中学生、高校生のころ、しんどくても頑張っていたんで、全く理解ができなかった。大学にもひとり親家庭の出身者はいましたが、みんな頑張る子でした。渡塾で出会った子はそうじゃない子もいて。

――自分の経験とのギャップを感じたわけですね。
そうですね。でも、実は勉強になかなか手を付けない子どもの背景には、日常生活が全く安定していないっていう問題がある場合もあって。
親が離婚して心が不安定だったり、父親から虐待を受けていたり、親子関係がすごく悪かったり、学校にも馴染めていなかったりして、ずっと心にモヤモヤを抱えている子もいます。
僕も中学時代は家にいるのがつらかったんですが、それでも、幼少期が比較的安定していたので、土台はしっかりでき上がっていたんです。
僕は「幼少期の貯金」って呼んでるんですけど、そのおかげで、中学で不安定な時期が来ても土台はゆらぎませんでした。でも、渡塾で出会った子どもたちの中には、そもそもの土台がない子もいた。

だから、「ただ、勉強を教えるだけじゃだめなんだ」って思うようになって。日々の中に「安心」を作っていかないと 、将来のことを考えることもできないなって。それを子どもたちから教えてもらったんです。
――渡さんが思う「安心」ってどういう状態ですか?
「自分はひとりじゃない」って思えることかなって思っています。味方がいるというか、何があっても大丈夫と思えるというか、そういう感覚を持てる状態が僕の考える「安心」ですね。そういった「安心」の土台があって初めて、人は学ぶことができるんじゃないかと。
例えば、心のもやもやがあって、家で宿題ができない子がいる。普通の塾だったら、「なんで宿題やってこないんだ」と怒る。僕も昔はそうでした。でも、渡塾の講師は「なんで宿題をやってこなかったんだろう」と思いを馳せる。
家に勉強する環境がないかもしれない。親とけんかしたのかもしれない。妹や弟の世話をしないといけなかったのかもしれない。子どもの行動の背景に何があるのかを、まずは想像しています。

そうすると、塾に休まずに来てくれただけでも、「えらいやん」ってなる。遅刻せずに塾に来ることも、宿題をしてきたことも、それが決して当たり前ではないということに気づきます。
だから講師は、子どもの小さな行動を見逃さず、子どもたちの頑張りをしっかりとほめるようになります。そういう人がいる空間は、子どもにとって安心できる場になるのではないかと。安心できる場になると、授業がない日にもふらっと子どもは塾にやってくることがあります。

――特に印象に残っている生徒はいますか?
印象に残っているのが、初期のころに通ってくれた生徒。当時、中学2年生のひとり親家庭の子どもでした。勉強が苦手で、5教科で合計100点台だった子でした。その子は半年で200点くらい成績が伸びたんです。
「なんでそんなに伸びたの?」って聞いたら、「渡塾の先生は、僕のことほめてくれた。これまで誰もほめてくれんかったから」と。その子のお母さんは朝から晩まで働いていて、子どもとじっくり関わる時間がなかったんです。学校にも行ってない子だったから、日常の中で「人にほめられる」って経験が全くなかったんです。
その子は「自分はできない」って思い込んでいました。「ひとり親家庭やから、自分はあかん」と言っていた。でも、ひとり親家庭で育った僕や大学生に出会って、「ひとり親家庭でも大学に行ける人っておんねんや。塾も立ち上げたんや。もしかしたら自分も何かできるかも」って言ってくれたんです。

――渡さんは子どもたちのロールモデルにもなっているんですね。
僕たちが描いている塾のビジョンは、「俺も一年前はそういう感じだったわー」と話してくれる先輩がいて、後輩は「自分は今しんどいけど、先輩にみたいになれるんや」という気持ちになれる場所にすることなんですね。「その生き方で誰かの支えになれる」という言葉を使っているんですけど。
これは僕と生徒に限らず、講師と生徒、もっと言えば、生徒の間でもできるんじゃないかなと思います。だから、塾での出会いを大切にしてほしいですね。

――子どもたちは、悩みを塾で相談することもあるんですか?
子どもたちは、家庭で悩んでいることがあっても、最初はあまり顔に出さないです。
だから、面談をセッティングして話を聞くというよりも、授業が終わって講師が子どもを家の近くまで送る時や、授業がない日に子どもがふらっと塾に来てボーっとしている時に、家族関係、学校の友人関係の悩みをぽろっと吐き出してくれる時がありますね。
渡塾は、「塾」という場だからこそ、悩みを抱えた子どもたちとつながり、安心してもらえる空間をつくることができると思っています。
例えば、安心できる居場所がない子どものための「相談の場」を作ろうとしても、それをうたった場所には、なかなか子どもは行きたいとは思わないですよね。少なくとも僕はそうでした。
「勉強しに行く」っていう大義名分があるからこそ、親にも「行ってきます」と胸をはって言えると思うんです。

費用は誰が負担するのか?
――塾の授業料はどうしているのですか?
一般的な塾と同じように、保護者から授業料をいただいて塾を運営しています。ただ、ひとり親家庭だと料金が半額になります。
週1回の授業で通常12,000円のところを、ひとり親家庭の場合は月6,000円。一般的な個別指導塾だと月20,000円以上するところもあるので、比較的安価です。
受験生でもう一コマ授業を増やしたい場合でも、親に気を使って言い出すことができなかったり、増やすことができなかったりすることもあります。
その場合、塾に「奨学金制度」があり、子どもは家庭の負担なしで授業を増やすことができるようにしています。奨学金を受けるには、面談などの審査をします。この奨学金は寄付金を財源にしています。

――経済的な理由で授業料の負担が難しい家庭もあるということですね。
僕もそうでしたが、渡塾に来る子ども、特にひとり親家庭の子どもは「親に迷惑をかけないようにしたい」って気持ちは強いと思います。親に負担をかけたくないから塾をやめると言ってきた子もいました。
それが「学びたい」っていう意欲を阻害してしまう場合もあるのが実情です。大学まで行きたいけど、奨学金を借りなければならず、将来返せるのかと不安に思って諦めようかと相談しにくる子もいます。

――そもそも教育の費用は誰が負担するべきだと思いますか?
難しいところです。一般的に塾代などの費用が高すぎるのは課題だと思うのですが、僕は最低限の受益者負担は、大事なことではないかと思います。子どもは、経済的に苦しい中でも、親が払ってくれていると感じることがやる気につながることもあります。
また、支援者としても子どもや保護者と対等でいられるので、良い関係でいられるという面もあります。これが一方的にボランティアで教えるとなると、支援している側と支援してもらっている側がでちゃうこともあるんじゃないかとも思います。

でも、最低限でも家庭で負担できるところは負担してもらいつつ、それでも払えないところは出てくると思うので、そこは公的なお金で支えられるなりして、経済的な事情であきらめることがないような仕組みがいると思います。
ちょうど、箕面市でも、今年から試行的に学校外教育費の援助制度が始まるようです。僕らは今、保護者の負担が足りない分は寄付金で賄っていますが。
――確かにそういう側面もありますね。今後活動はどのように展開していきたいですか?
渡塾は変わらず続けていきたいと思います。子どもたちが安心できる空間を作り続けたい。しっかりと地域に根付いて、教室を増やしていくことにチャレンジしたいと思っています。

あとは、子どもの貧困対策、ひとり親家庭支援というと、おおげさなイメージを持ちがちですが、子どもたちの周りにいる人々が理解者、共感者になってくれることがとても大切だと思っています。
例えば、近所のお父さんが子どもと釣りに行く時、ひとり親家庭の子どもも一緒に連れていってくれるというようなことですね。日常の中で、ほんの少し手を差し伸べてくれるのが嬉しかったりする。
そうなると、支援の網の目がどんどん細かくなっていく。そんな社会を少しでも実現できるよう、まずは地域でしっかりとした仕組みを作っていくことが目標です。
――支援の輪が広がっていくといいですね。今日はお話を聞かせていただきありがとうございました。

《取材後記》
今回お話を伺って、渡さんの「ただ、勉強を教えるだけじゃだめなんだ。」という言葉が印象に残った。この気づきが、渡塾の方向性を決める大きな転換点となったのではないだろうか。
渡塾が果たす役割は、ひとり親家庭の中でも経済的に厳しい状況にある家庭の子どもたちに学習の機会を提供することだけではない。
家庭や学校に居場所がない子どもたちの「安心」の土台を作ること——。これこそが渡塾が担っている大切な役割だと思う。「安心」の土台があってこそ、人は「学ぶ」ことができる。
では、「安心」とは何だろうか。渡さんの言葉を借りると、それは「自分はひとりではない」と思えること、「味方がいる」と思えること——。つまり、「安心」を作るのは、人との関係だ。
人によっては、その役割を家族が担っているのかもしれない。学校の友人や教師かもしれない。

しかしながら、家族関係が壊れてしまった子どもたちがいる。学校での人間関係にしんどさを抱えている子どもたちがいる。「安心」の土台となる人との出会いは、決してすべての子どもたちにとって当たり前のものではない。
渡さんは、ゆっくりと時間をかけながら、家庭や学校で包摂できていない子どもたちとの関係を紡ぎ、子どもたちの心の中に「安心」の土台を作るお手伝いをしている。「学ぶ場」として存在する塾が、そんな役割を担い得るということを、渡塾は私たちに教えてくれている。
地域に、子どもたちと関わる多様な人々がいること。その出会いに経済的な制約を設けず、すべての子どもにそのチャンスがあること。これが、「安心」の土台を築くことができなかった子どもたちにとってのセーフティネットとなり得るのではないかと思う。

記事の最後に、渡さんとお母さんのその後をご紹介したい。実は、1年ほど前に、渡さんのお母さんは熊本から渡塾の近所に引っ越してきた。渡塾の一番の応援者として、渡さんたちの活躍を傍で見守り続けている。時には、渡塾の寄付集めも手伝ってくれているそうだ。
渡さんは、「中学時代、家庭がどんなにしんどい状況でも、僕の土台は揺らがなかった」と話してくれた。彼の「安心」の土台を築いたのは、まぎれもなくお母さんの存在だと思う。お母さんへの感謝の思いを胸に、渡さんは、これからもこの町で、子どもたちを優しく見守り続けていく。

*「渡塾」を運営する「NPO法人あっとすくーる」へのご寄付はこちら
(執筆:今井 悠介)
(写真:久米 凜太郎)
(編集:辻 和洋)