学生ボランティアが伝える“それぞれの3.11”
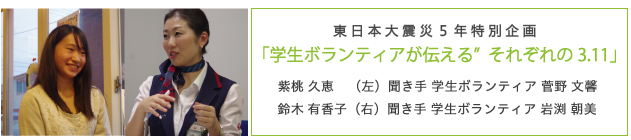
CFC学生ボランティアの岩渕です。
来月、3月11日で東日本大震災から5年を迎えます。チャンス・フォー・チルドレンではこの間、述べ400名以上の学生ボランティアが活動してきました。ボランティアの中には東日本大震災で被災した者もいるし、被災地にいて何もできていないもどかしさを感じていた者もいます。そんな私たちはこの4年半、子どもたちに寄り添い、その声を聴き続けてきました。
今回の企画はそんな私たちの思いから始まりました。クーポン利用者、それを支援する企業の社員。私たちが見た“それぞれの3.11”を伝えます。

道端や郵便ポストの上など、見渡すと様々なオブジェがある石巻の商店街。休日なのに人通りが少なく、4年半経った今も改修工事が終わっていない商店を見ると、震災の大きさを感じる。この商店街を通って毎日通学している紫桃久恵(しとうひさえ)さん(16)は、現在石巻にある高校の1年生。その高校は、「あの高校、課題が多いことで有名らしいよ。」と話題だった。入学当初は時間がないと感じていたが、最近は「(課題の量に)慣れてきましたよ!」と話す。日付が変わる頃まで毎日学校の課題に取り組み、勉学に励んでいる。その源となっているのは、「将来は通訳になりたい」という強い思いだ。
初めて怖いと思った自分の街
2011年3月11日。その日は紫桃さんにとって、いつもと変わらない朝だった。小学校1年生から続けていたピアノを練習するため、朝6時に起き2時間練習していた。4月からは6年生になる。「ピアノももっと上達したいし、勉強も頑張らないと」。雪もちらつく肌寒い日だったが、新学期のことを考えるとワクワクしてきて、暖かかった。
もうすぐ下校する時間。紫桃さんは小学校で突然大きな揺れに襲われた。地震が引き起こした津波は校庭まで押し寄せ、水が引くまでの間、小学校で家族の迎えを待った。一緒に待っていた友達は続々と家族と再会していく。自分にはなかなか迎えが来ない。「お母さんいなくなっちゃったのかな」。一瞬、頭によぎった不安を振り払う。すると更に大きな不安が押し寄せてくる。「お願い、お母さん早くきて」。
家族と再会できたのは震災発生から1週間後。小学校では一番遅い迎えだった。外に出ると被災した自分の街を初めて見た。かろうじて原型をとどめた土まみれの道路。散乱しているがれき。濁流になっている川の水。住める状態ではなくなった自分の家。いつもサイクリングロードから「きれいだな」と見ていた川に、初めて「怖い」という感情を抱いた。「これからどうなるんだろう。」不安な気持ちでいっぱいだった。
関西で感じた復興への希望
震災によって家が住める状態ではなくなったため、半年間、大阪の親戚にお世話になることになった。新しい街への引越しは、石巻から離れる不安と家がある安心感が入り混じった複雑なものだったが、すぐに友達ができ、特別扱いすることなく接してくれたことで、少しずつ和らいでいった。
ある時、親戚に連れられて、関西の街を見に行った。その中には阪神・淡路大震災で大きな被害を受けた場所もあった。「当時はこうだったんだよ」と親戚のおじちゃんが教えてくれたが、現在の光景からは想像もできないものだった。「関西だって復興したんだから、きっと石巻もよくなっていく」。遠く離れた大阪から、自分の街のことを思った。
石巻へ戻ることが決まり、大阪を離れる直前に担任の先生が言ってくれたが言葉がある。「震災から何もかも始まっていく、君らが作っていくんだぞ」。いつまでも震災を引きずっていてはいけない。「自分にできることを頑張っていこう」。新たな気持ちで石巻に戻った。
人と人とをつなぐ「通訳」になりたい
紫桃さんは、中学生になった時から「通訳」という夢に向かって毎日勉強に励んでいる。
最初のきっかけは母が外国人だったことであり、次のきっかけは震災直後に出会った外国人の学習ボランティアだ。小学4年生の頃から漠然と「外国に関わる仕事がしたい」とは思っていたが、震災後に実際に外国人と触れ合い、勉強を教わったことが最も印象に残っている。
異国で起こった大災害に対してすぐに現地に駆けつけ、片言ではあったが私たちに英語を教えてくれ、「がんばれ」と励ましの言葉も掛けてくれた。緊張してしまってうまく話せないこともあったが、恐怖や不安の毎日の中で、笑顔を届けてくれた。小学6年生の紫桃さんは、何を習ったか具体的に覚えていないというが、「こういうことができる大人になりたい」と強く思ったことは鮮明に覚えている。
中学校に入ってからは、夢に向かって苦手な数学の勉強にも励み、CFCクーポンももらって学習塾にも通うことができた。無事、第一志望の高校にも入学し、目標に向かった実践的な勉強にもチャレンジすることができている。勉強でいつも心がけているのは、毎日コツコツ積み重ねること。英単語には毎日触れるようにし、苦手な数学の問題にも積極的に取り組んでいる。その先で目指すのは、国際系の大学へと進学すること。あの震災の時のボランティアのように人と人とをつなぐことができる存在になること。
「コミュニケーションの壁をなくすお手伝いをしたい」。大いなる夢の実現に向け、1人の高校生が次なるステップへの道を歩み始めている。
そんな紫桃さんを支援する企業のひとつが、日本航空株式会社(JAL)です。
JALの社員の中には東日本大震災で被災した仙台空港の職員さんもいます。その方々は当時何を思い、そして今、何を考え子どもの支援をするのでしょうか。震災当時から仙台空港で働いていた旅客部の鈴木有香子さん(40)、震災直後にJAL仙台空港所長に着任した上原博信さん(52)に話を伺いました。

「そのネイルかわいいですね」、「今日はお帰りが早いんですね」。国内外からたくさんの人が集まる仙台空港で、今日も鈴木さんは笑顔でチェックインカウンターに立っている。アシスタントマネジャーとして従業員の管理業務やオフィスワークを行う一方、「お客様との会話の時間を最も大切にしている」。しかし、以前の鈴木さんは仕事のスピードと正確さを売りにしていた。その時はお客様とゆっくり会話をする自分の姿は想像できなかったという。東日本大震災の経験が自分を大きく変えた。
仙台空港を襲った大災害
東日本大震災発生時刻の6分前、14:40発のフライトのカウンターインチャージを担当していた鈴木さんは、飛行機が飛び立った様子を見届け、先輩と休憩室で休んでいた。その時、大きな揺れと共にポップコーンのようにたくさんの機材が跳ね、エラー音が鳴り響いた。普段は大人でも動かすことが難しい金庫ががたがたと揺れ、鈴木さんは「もうやめて」と心の中で叫んでいた。
揺れが収まると、スタッフは空港内のお客様の安全確認に向かった。役割分担をしていたわけではないが、自然と自分たちがやるべきことを理解していた。空港は天井も含めガラス張りのため、落下による怪我が心配された。お客様にはすぐに外で待機するように避難を指示したが、本社と連絡をとっていたスタッフから無線で連絡が入った。「津波がくる」。
近くの老人ホームや近隣住民も空港に避難してきた。全員が建物内へ入った頃、大津波が空港に押し寄せた。車や家が団子のように流されてくる様子を皆が空港内から見ていた。「どうしよう、どうなるんだろう」。津波とともに恐怖と不安が押し寄せてきた。
夜を迎え、2時間交代で見回りをしながら空港に避難したすべての方の名前を聞いて回った。すると、あるスタッフが子どもと抱き合っている姿が目に入った。「知り合いだったの?」と尋ねると、そのスタッフは「違う」と答えた。子どもの父親は消防士で、震災が起きて見回りにいって津波に流されたという。震災前日は父親の誕生日。「プロミスリングを作ってプレゼントした」という話を聞いたが、そのスタッフは「何も声を掛けてやれず、ただただ黙って抱きしめていた」と話した。
希望に見えた飛行機
震災から1週間後、鈴木さんのもとへ1本の電話が届いた。「1ヶ月後に飛行機を飛ばしたい。その立ち上げメンバーに入ってもらえないか」。電気も水道もない空港で、自家発電で搭乗手続き等を実施し飛行機を飛ばずという前代未聞の挑戦だった。チェックインや誘導方法など、お客様を迎えるために必要な準備に取り掛かったが、空港内はとても始動できる状態ではなかった。1階部分は自分の背丈より高いところまで泥がついていた。オフィスも使える状態からはほど遠く、1ヶ月後という目標が現実的とは思えなかった。
そんな時、全国各地の社員ボランティアが車を相乗りして駆けつけた。清掃業者がくるので大丈夫といっても「いいからいいから」と無言でモップをかけてくれた。鈴木さんはその姿を今でも鮮明に覚えている。給料もでない、頼まれてもいない。しかし、黙って掃除を続けるボランティア。「私も受け手ではいけない、この感謝の気持ちを伝えていこう」。自分の中に芽生えた確かな気持ちを感じていた。
震災後、最初の飛行機は4月13日に仙台空港に着陸した。震災から1ヶ月と2日のことだった。鈴木さんは仙台市内に設置された指揮所でその様子を見守っていた。今まで毎日飛行機を見ていたはずだったのに、「飛行機ってすごいな」。涙が止まらなかった。
一輸送機関にしたくない
これまで支援をしてもらった感謝をどのように伝えていくか、鈴木さんは考えていた。社員だけでなく、多くの関係者やボランティアが支援をしてくれた。日本だけでない世界中の方々が仙台空港を応援してくれた。消防士の父親を亡くした子どもとスタッフが抱き合う姿や、黙々とモップをかけてくれたボランティアの姿を思い出した。「私は彼らに何を伝えたらいいんだろう」。
そんな時、仙台空港所長に着任した上原さんは、「まず、目の前にいるお客様に感謝を伝えよう」と鈴木さんに話した。多くのお客様が「震災大変だったね」と声を掛けてくれる。そのお客様にもっと喜んでもらえるサービスを考える。鈴木さんの仕事に変化が生まれた。
最近は、地元の小学校にも出向き、航空教室などの出前授業をボランティアで行う。紫桃さんなど、CFCクーポン利用者を仙台空港に招いて交流会も行った。まだまだ足りないが、少しずつ与えてもらったものを還元していければと思う。私たちの仕事は、お客様を安全に目的地に運ぶだけではない。お客様に楽しんでもらい、感謝を伝えることも大切だ。空港をハブとして人の輪を広げていきたい。CFCの子どもの支援もその1つだと思っている。

「誰が被災者なのか。」鈴木さんとの話を終えた後、上原さんはそんな問いを発しました。
「仙台空港で言えば、そこにいたすべての人が被災者だった。しかし、航空会社のスタッフやその他空港関係者、そして避難していた一般のお客様の一部も安否確認や避難住民のケアを行い、老人ホームから避難をしてきた方の汚物処理も行った。そのことが大変だったとか、素晴らしかったというつもりはない。ただ、被災者と支援者という一方的な関係や見方を、私たちはそろそろ変えていく時期にきているのかもしれない」。この上原さんの話は、私の心に強く残りました。
そして同時に、私たちの活動のスタンスにも通じるものがあると感じ、とても共感しました。私たちは、紫桃さんや被災した子どもを「かわいそう」という庇護の対象とは見ていません。「東北の未来を一緒に担っていく仲間」だと思っています。その思いは、震災から5年が経った今も変わっていません。
文章:学生ボランティア 菅野 文馨 岩渕 朝美
