法人設立14年を迎えて(代表理事・奥野慧)

代表理事の奥野です。本日6月20日、CFCは法人設立から14年を迎えました。
温かいご支援により当法人の活動を支えていただいている皆さまに、心から感謝を申し上げます。
子どもたちを包摂する地域社会をめざして
スタディクーポン事業では、2024年度、新たに3つの自治体との協働がスタートし、協働自治体数は9自治体(※全国的には約30の自治体が実施)となりました。
スタディクーポンの政策化は年々広がりを見せていますが、背景には教育格差の拡大と、自治体で多様な学びを支援する必要性の高まりがあるのではないかと考えています。
経済困窮家庭のみならず、障害や不登校、外国にルーツがあるなど様々な背景を持つ子どもたちにどう対応していくかを考えた時、彼ら彼女らの多様なニーズに応えるには、学校教育に加え、放課後の学びをどう支えるかが重要です。
CFCが持つスタディクーポンのしくみは、様々な背景と特性を持った一人ひとりに対応し、子どもたちの放課後の選択肢を広げるうえで重要な役割を果たしているのです。
自治体との協働では、ただ対象者にクーポンを届けるだけでなく、家庭を取り巻く環境や、届けた先の子どもが意思決定に至る過程にもアプローチすることを大切にしています。

たとえば、自治体職員やケースワーカーを対象にした説明会では、システムの使い方だけではなく、CFCが大切にしている理念をしっかり共有することを意識しています。
実際、制度の意義を深く理解したうえで家庭に働きかける自治体ほど、クーポンの利用率も高くなる傾向にあり、必要とするすべての子どもが制度を利用できるようにするためには、子どもの周辺で利用を支える大人たちの存在が不可欠なのだと感じます。
また、子どもたちと定期的な面談を行うブラシス(ブラザー・シスター)は、子ども自身の声に耳を傾け信頼関係を築くことで、子どもの自由な意思決定プロセスを支えています。
行政のケースワーカーや職員とは異なる立場から子どもにアプローチできるブラシスもまた、子どもの選択権を保障するうえで欠かすことのできない存在です。
スタディクーポンの仕組みをいかに広げていくかも大切ですが、クーポンの仕組みを取り入れた上で、いかに子どもたちを包摂する環境を地域に根付かせていくかも、CFCが自治体と協働することの大きな意味ではないかと思っています。
被災地域のニーズに即した放課後の学び保障
2024年元旦に発生した能登半島地震を受け、CFCでは被災家庭の子どもたちの学びの機会を守る緊急支援事業を開始しました。
(参考:24年度・25年度の支援実績)
能登半島地震では、沿岸部から比較的内陸に近い地域まで、被害が広い範囲におよびました。
地域ごとの支援ニーズも様々で、奥能登では学習塾や習い事の選択肢そのものが限られる中、放課後の部活動に参加する子どもの割合が大きい傾向にあります。
一方、金沢市などの地域では、受験対策のため学習塾や習い事に通う子どもが多い傾向も見られます。
地域ごとにニーズが異なる中、居住地や子どもの学年に応じて最適なかたちで支援を活用いただけるよう、今回の緊急支援では、学習塾や習い事のみならず、部活動の費用にも助成を利用できるようにしました。
災害支援として部活動も含めた放課後の学びを保障するしくみは他にはなく、自治体や現地の支援団体からもこの点を高く評価いただいているのではないかと感じています。

ご家庭からの声(例)
野球のグラウンドが震災で使えなくなり練習する場所もなく貸してくれる遠くのグラウンドへの移動にかかる経費や遠征費が多く多額の費用がかかります。また、部活で使用する用具の買い替えなどにも費用がかかります。
自宅の修理にもお金がかかる中 大変だけど子供にはやりたいことをさせてあげたいです。
CFCではこれまでにも様々な緊急支援事業を行ってきましたが、過去の経験をふまえても、平時から社会的・経済的に困難な人ほど必要な支援が届きにくく、また先行研究でも、子どもたちへの影響は時間が経過した後に表面化することもわかっています。
災害のような突発的な出来事により貧困状態に陥った家庭や子どもたちにできるだけ早い段階で必要な支援を届けることは、貧困の長期化・固定化を防ぐ予防的な観点からも非常に重要です。
今回の能登半島地震に限らず、今後とも過去の緊急支援での経験を活かしながら、被災地域での多様な学びを支える活動を行っていく予定です。
多様な学びを通じて子どもや家庭を包摂する社会を目指し、15年目も真摯に活動を続けていきます。
活動を応援してくださる皆さまにも、引き続き私たちとともに歩んでいただけたら幸いです。
子どもたちの学びをともに支えていただけませんか
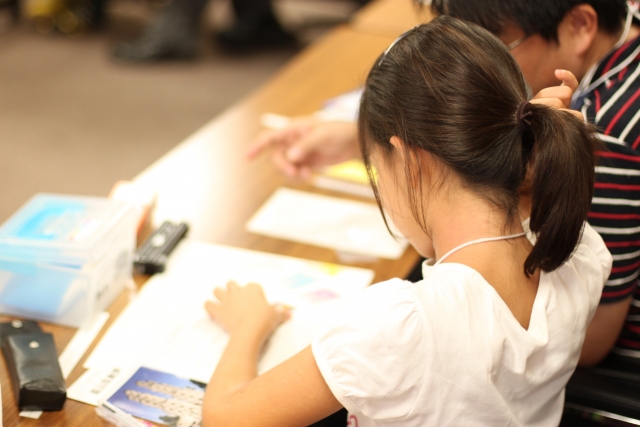
CFCでは、毎月1,000円~のご支援で子どもたちの「学びたい」という気持ちを継続的に応援することができる「サポート会員制度」を設けています。困難な状況下にある子どもたちが学びをあきらめることのないよう、温かいご支援をいただけますと幸いです。